遠くで、雷が鳴っている。
クリムゾンはそれを夢現で聞いていた。
起きているのか、それとも本当は、眠れないという夢を見ているだけなのか。己にも良くわからない曖昧な境界で、クリムゾンはたゆたっていた。
隣で横になっているシュザンヌもあまり眠れずにいるのか、頻繁に寝返りを打っているようだった。声をかけて見た方がいいかと一瞬迷い、だがどんなに浅くとも眠っていたとしたら……。起こしてしまったら可哀相だと、思いとどまる。
雷は少しずつバチカルに向かって来ているようだった。
この季節は嵐が多いとは言え、今日のこれはかなり激しい。雨音が一度気になり出すと、ますます目が冴えた。クリムゾンは準王族扱いの貴族ではあるが、武門の名家、ファブレ家の総領としてまだ幼少の頃から戦場に立ち、譜術による轟音、砲術による爆音、破壊音、悲鳴──そういったものが飛び交う激戦の最中にあって、きっちりと睡眠を取ることの出来る剛胆な男だ。どんなに激しくとも、今更風雨の音ごときで眠れなくなることなどないはずなのだが。
このところ山ほど抱え込んでいる心配事の数々に、もうずっと眠りが浅いせいもあって、やっと眠れたと思っても些細な物音で敏感に目を覚ましてしまうのが常だったが、雷や雨の音が気になって眠れなくなるほどとは俺の精神も弱くなったものよ、とクリムゾンはぼんやりと自嘲した。
隣で、またシュザンヌが寝返りを打った。
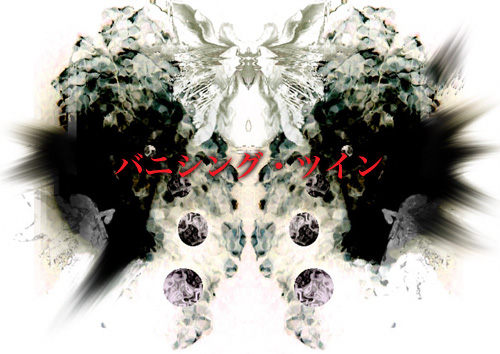
生温く湿った風が頬をかすめ、クリムゾンはふ、と目を覚ました。
眠れない眠れないと思っていたのはやはり夢だったのか。あるいは苦しんでいるうちにうとうとしてしまったのか。
疲れは抜けるばかりか、眠るたびに増して行くようだ。身体は重く、頭は軋む。
また、雷が鳴った。稲光は、まだやや遠い。
耳に、ざあっざあっと雨が木々を叩く音が聞こえる。明日は──もう今日かも知れないが──止むだろうか。登城して陛下に暇乞いをし、昼過ぎにはベルケンドに出立せねばならないというのに、これでは視界が悪いどころか、海の荒れようによっては船が出ない可能性もあると考え、さらに憂鬱な気分になり、小さく溜め息をついた。
その途端、喉にちくりとした痛みを感じ、クリムゾンは瞬時にはっきりと覚醒した。
ゾッと鳥肌が立ち、じわりと汗が滲む。日の出までにあとどれくらいあるのか、寝室の中は家具の陰しかわからないほど真っ暗なまま、物音一つしない。──いや。何故気付かなかった? 微かに、本当に微かに、ぽつ、ぽつと水滴が落ちる音が聞こえる。だが、意識しなければ見過ごしてしまったその音によって、彼は枕元により深い闇が凝っているのに気付き、密かに唇を噛んだ。
──侵入者。
このファブレ邸の奥深く、当主の寝室にまで誰に気付かれることもなく入り込んで来た者がいる。考えてみれば、動く者なき室内で空気が揺らぐことなどあるわけがなかった。
(この俺としたことが、喉元に剣を突きつけられるまで侵入者に気付かぬとは……!)
クリムゾンが目を覚ましたことに気付いたらしい侵入者が、微かに身じろぎをする。
(シュザンヌは……眠っているか)
寝返りを繰り返していたシュザンヌが、身動き一つしないのを確認し、クリムゾンはほっと息を吐いた。
「……何者だ」
侵入者を刺激しないよう、なんとか眠りを得ることが出来たらしいシュザンヌを気遣い、静かに問うと、侵入者は詰めていたらしい息を、溜め息のように長く吐いた。
「貴公のご子息のことで、伺いたいことがある」
おそらくクリムゾンと同じく、シュザンヌを起こさぬよう気を使っているのだろう、低い声を更に潜めて侵入者が答えを返した。声だけを聞けば、案外若い。一体いくつくらいの者なのだろう。この屋敷の警備は甘くない。ファブレ家の私兵、白光騎士団が常時屋敷の内外を警備しているのだ。視界の悪い嵐の日とはいえそれをなんなく潜り抜け、しかも現職の元帥に気配を悟られることもなく寝室まで入り込み、喉元に剣を突き付けた強者の声としては、若すぎて意外なくらいだった。
「我が息子は一月ほど前に姿を消した。未だ行方が知れぬままだ」
嘘ではなかった。
バチカルを脱出したあと、息子のルーク──正確には息子のレプリカだが、まあどちらも息子であることに変わりはあるまい──とその一行がファブレの領地、ベルケンドに滞在していたところまでは分かっている。だが、息子は、誰にも知られず忽然と姿を消した。ランド・スチュワードからの知らせが来てすぐにベルケンドへ戻り、自ら指揮して捜索したが、息子は見付からないまま今に至る。
レプリカは死すれば、その存在の証を何も残さぬという……。クリムゾンは書庫からレプリカに関する書物をすべて隠し、レプリカがどういうものか例え知っていたとしても決して夫人の耳に入れるなと厳命を出さねばならなかった。
不安と焦燥を声に含めぬよう気をつけて答えると、声を発した訳ではないが、クリムゾンは男が嗤った気配を感じた。
「ご子息は俺がお預かりしている。──ああ、髪の毛一筋たりとも傷つけてはいない。その点はご安心いただこう」
クリムゾンは暗闇の中、カッと目を見開いた。一瞬にして、体中の血が沸騰してしまったかのように熱くなる。目の奥の奥から、何か熱く、込み上げてこようとするものを、目をしばたかせて必死で堪えた。「髪の毛一筋たりとも傷つけてはいない」あの子は、生きている?!
──生きていて、くれたのか……!
「──要求を聞こう」
安堵のあまり震える声を出来るだけ押さえながら、クリムゾンは侵入者に言った。息子を無事に返して貰えるのならば、いかなる要求でも飲むつもりだった。
「ご期待にお応え出来ず、申し訳ないが、貴公に要求することは何もない。欲しいものはすべてご子息本人から頂戴している」
「息子に何を……」
ぐっとより強く押し付けられた剣先に口を閉じると、笑い含みの声が低く、囁いた。
「なに、大した要求はしていない。俺の身の回りの世話をお願いしているだけだ──ご子息は可愛いな? 俺の身体の下で快楽にむせび泣く姿が、実に素直だ。初めは痛めつけるつもりで無理に犯してやろうと思ったが、どういうわけか全く抵抗が無かった。こちらで良く躾けられたようだな。そのため結果的に彼を傷つける必要がなかった──良かったな?」
「…………!」
クリムゾンは大声を上げそうになるのを必死で押しとどめた。
(では……では! この男の言う身の回りの世話とは……)
男の台詞から、今現在ルークが置かれた状況がはっきりと分かった。
男への怒りと、己への侮蔑、息子への哀しみ、憐れみで目が眩む。
──彼の息子がその行為に抵抗するはずなどなかった。求められたらすぐに応じるように、そのことに疑問を持たないように、それがこの家における彼の最も重要な仕事だと、そう──まるで男娼のように育てたのだ。相手が男であっても抵抗しなかったというのは、倫理観を注意深く遠ざけた弊害に過ぎない。そもそも男女の性の違いなど、あの子が理解していたかどうか。
そうだ、あの子には何も知識を与えていない。いや、ある部分では過剰なほどの知識を与えたが、その他のことでは余計なことを彼が知ったりしないように……あの行為が本当は愛し合う者たちの営みであることを知ったがゆえに傷つくことのないよう、厳重に知識と倫理から遠ざけた。知らなかったこととはいえ、レプリカの息子はまだ幼児期にあったというのに……。
そのせいで、無知で無垢な彼の息子が、こんなならずものに付け込まれることになったのだ。
噛み殺し損ねた嗚咽が、喉の奥から小さく漏れた。
息子を愛したくなかった。いずれキムラスカの繁栄の礎となるために命を捧げる息子を愛してしまっては、その時に正気でいられる自信がクリムゾンにはなかった。だから遠ざけた。遠ざければ遠ざけるほど、息子は物問いたげな視線を向けてくる。その視線を受け止めることが出来ず、クリムゾンはますます息子から顔を逸らし続けた。何も知らない哀れなシュザンヌと息子の、ささやかな交流の場を目撃するのも苦痛だった。クリムゾンは、その暖かな日だまりに入る資格を持たない。家族の中で一人だけ、弾き出された存在だったのだ。己も、同じ家族であるのに……!
背中には、息子の視線を常に感じた。哀しみと、諦めと、懇願の視線を……。絡み付く視線から逃れるため、領地のベルケンドに籠り、妻をも捨て置いたまま、バチカルに上ることも稀になった。だが、ベルケンドにいてさえ、いるはずのない息子の視線を背に感じることがあった。皮肉なことに、どちらの息子の視線もだ。
視線を感じて後ろを振り返り、気付いた。
クリムゾンは、とうの昔に失敗していたのだ。
息子を愛さない、ということに……。
「先ほど、息子を傷つけてはいないと言わなかったか。心は、精神の傷はそれには該当しないということか」
「……ふ。心の傷? それどころかご子息はこの俺を大層気に入って下さったらしく、勿体なくも一生側から離れないようにとのご命令を頂戴したが。──苛めすぎてたまに泣かせてしまうかも知れないが、おおむね大切に可愛がって差し上げているつもりだ」
男はクリムゾンを怒らせたいのか。それとも嘆かせたいのか。
──どこまで本当のことなのだろう。息子が生きていると言うこの男の話を信用して、良いのか。
息子がどんな屈辱的な目に合わされているのかを、親である自分の前で殊更にいやらしく示唆する男に、夏掛けの下で握った拳が震えたとき。
ふいに横から、ひんやりとした骨張った手が、彼の拳に力を添えるように握られた。